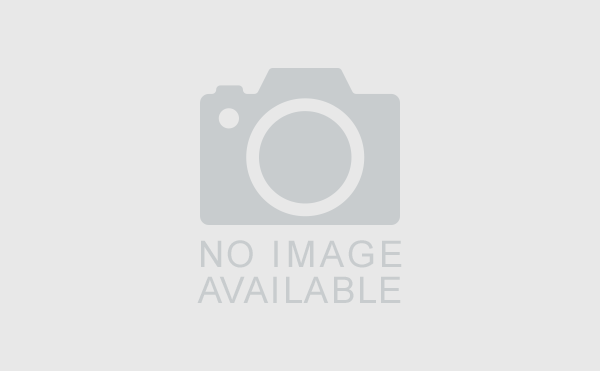【#162】サウナ
ゲームがお仕事になる「やさしさまんてん平野出戸」です!
就労継続支援B型「やさしさまんてん平野出戸」では初回に利用者さんの希望のゲームを導入しており障がいを持つ方でもストレスなくのびのびと楽しくお仕事に取り組める環境づくりを心がけてます😌
サウナのメリット、デメリットとは
発汗作用と自律神経の働きが「ととのう」カギ!?
「たくさん汗をかいてスッキリした!」。サウナに入った後、このような爽快感を味わったことがある人は多いのではないでしょうか。発汗作用はサウナの持つ大きな効用として知られています。発汗作用によって体内の老廃物が排出され、新陳代謝の促進につながります。サウナ浴で得られる爽快感も、この発汗作用によるところが大きいと考えられます。
また、サウナ浴中は高温により自律神経の一つである交感神経の働きが優位になります。交感神経が活性化することで心拍数が増加し、血圧が上昇します。一方で、温熱効果によって血管が拡張するため、サウナ浴後に血圧は低下します。
さらに、サウナ浴後の水風呂には次のような効果があります。
サウナ浴で高くなった体温を下げる
サウナ浴による発汗作用を抑える
しかし、水風呂は交感神経の働きをさらに活性化するため、血管が収縮し、血圧を上昇させます。普段の血圧に問題のない健康な人であれば、サウナの温熱による血管拡張と、水風呂による血管収縮をくり返すことで、血管の健康を維持するうえで重要な血管内皮機能の向上につながることが期待できます。
また、交感神経は自動車のアクセルに例えられ、体が温まったサウナ浴後はブレーキとなる副交感神経が優位になります。その結果、心身ともにリラックスし、心地よさを感じる場合が少なくないようです。これがいわゆる「サウナでととのう」といわれる状態なのではないかと考えられます。
大量の発汗による脱水に要注意
サウナには大きく次の2種類があります。
高温タイプ
80~100℃前後のサウナ。温浴施設には湿度が10~20%程度のドライサウナや80~100%のミストサウナが多い。
低温タイプ
40~60℃前後のサウナ。湿度が80~100%程度のスチームサウナ、ミストサウナのほか、湿度が65~70%程度の遠赤外線サウナなどがある。
スポーツに例えるなら、低温タイプのサウナはゆったりペースで走るジョギングですが、高温サウナ+水風呂は長距離をしっかり走るマラソンです。
体力がない人や普段から血圧が高めの人、高齢の人や疾患のある人などには、サウナと水風呂の交代浴は体への負担が大きかったり、血圧が急激に高くなることがあるため、高血圧を悪化させたりする原因になるので注意が必要です。体力がある人でも、気分が悪くなるまで無理してサウナ浴をすることは避けましょう。自分が快適だと感じる時間を目安にすることが大切です。
また、発汗作用はサウナの効用の一つですが、一方で発汗が進むと脱水のリスクが高まります。脱水によって体内の水分が減少すると血液の濃度が高くなり、血栓ができやすくなります。血栓は血管を詰まらせ、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす原因にもなります。
サウナ浴の前後に、少なくともコップ1杯分の水や麦茶を飲みましょう。ジュースといった糖分を含む飲み物はなるべく控えることをおすすめします。
なお、「サウナ浴後に冷たいビールを飲みたい」という人もいるかもしれません。アルコールには血管を拡張する作用があるため、健康な人であれば適量を飲むのはあまり問題ないでしょう。ただし、アルコールには利尿作用があるため、水分補給の代わりにはならないということを覚えておくことも大切です。また、飲酒後のサウナ浴は脱水を進行させる原因になるので避けてください。

サウナ浴は生活習慣病の発症リスクを下げる?
サウナ発祥の地といわれるフィンランドのサウナ浴は、日本と比べて低温で高湿なのが特徴です。フィンランドでは病気の予防効果や健康への影響についての研究が進んでおり、次のような報告があります。
●定期的なサウナ浴で高血圧のリスクが低下
高血圧の既往のないフィンランドの42歳から60歳の男性1,621人を対象に、約25年間追跡したKIHD研究で、週1回のサウナ浴群に比べて、週2~3回のサウナ浴群は高血圧のリスクが17%低く、週4~7回のサウナ浴群は47%低かった。
●サウナ浴の回数が多いほど心血管疾患のリスクが低下
フィンランドの42歳から60歳の男性2,315人を対象に、前向きに約21年間追跡したKIHD研究で、週1回のサウナ浴群に比べて、週2~3回のサウナ浴群は心血管疾患のリスクが27%低く、週4~7回のサウナ浴群では50%低かった。
ただし、通常の高温ミストサウナ浴は、不安定狭心症や発症3カ月以内の心筋梗塞、重症の大動脈弁狭窄症では病状の悪化や突然死の可能性があるため推奨されません。
一方、安定狭心症や慢性期の心筋梗塞ではサウナ浴が可能な場合もあります。
●サウナ浴の回数が多いほど認知症の発症リスクが低い
フィンランドの30歳から69歳までの13,394人の認知症と診断されていない男女を対象に、39年間追跡した結果、1,805人が認知症と診断されたが、そのうち1カ月あたり0~4回のサウナ浴群に比べて、9~12回のサウナ浴群は認知症の発症リスクが19%低かった。
ただし、軽度から中程度の熱ストレスは認知能力を改善する可能性がありますが、高度の熱ストレスは認知能力を損なうことが示唆されているので、特に高齢者の高温でのサウナ浴には注意が必要です。
生活習慣病などの治療に用いられる「和温療法」とは
一般的な温浴施設のサウナとは異なる、60℃の遠赤外線乾式サウナ装置(和温療法器)を用いた「和温療法」による、心不全や閉塞性動脈硬化症(ASO)、生活習慣病に対する効果については下記の論文にまとめられています。
和温療法では、60℃のサウナ室内に15分間入浴し、出浴直後にリクライニングシートに移動して、30分間、毛布で体を包んで保温します。高温サウナのように体の表面を過度に温めることなく、気持ちよく深部体温を上昇させるのが特徴です。また、温水浴ではないため、水圧の影響による心臓への負荷が少なく、重症心不全の治療にも期待できます。
■和温療法の一例
サウナ浴を60℃で15分間行い 、その後リクライニングシートで安静保温を30分間行う。
心不全や動脈硬化、高血圧、糖尿病、肥満などの生活習慣病リスクがある場合は、和温療法を行っている医療機関で相談してみるのもよいでしょう。