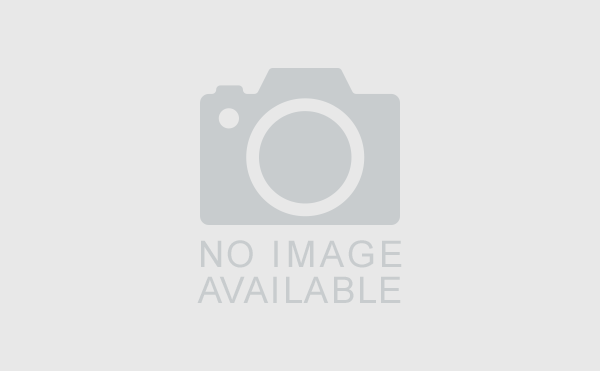🦝 タヌキ ― 里山に生きる知恵者
ゲームがお仕事になる「やさしさまんてん平野出戸」です! 就労継続支援B型「やさしさまんてん平野出戸」では初回に利用者さんの希望のゲームを導入しており障がいを持つ方でもストレスなくのびのびと楽しくお仕事に取り組める環境づくりを心がけてます😌
日本の里山や田畑、時には街の周辺でも、その姿を見かけることがある生き物――それがタヌキです。 丸い体、愛らしい顔、特徴的な黒い目のまわりの模様。 見た目の可愛らしさから、民話や昔話にも登場し、人々に親しまれてきました。 タヌキは主に夜行性で、昼間は木の陰や土の穴で休み、夜になると活動を始めます。 雑食性で、果実や木の実、昆虫、小動物、時には人間の食べ物まで幅広く食べるため、里山や農村の生態系において重要な存在です。 その食性の多様性が、タヌキの生き延びる力を支えています。

タヌキの行動で特に興味深いのは、体の柔軟さと狡猾さです。 民話では化けることができると描かれますが、実際にもタヌキは環境に合わせた生活術を持っています。 物陰に身を潜める、道端に落ちた食べ物を効率よく探す、冬眠はしないが寒さを避ける工夫をする―― その知恵深い行動が、人々に「里山の知恵者」として映る理由かもしれません。 また、タヌキは日本文化と深く結びついています。 昔話や絵本、信楽焼のタヌキの置物に象徴されるように、豊作や幸福の象徴として人々に愛されてきました。 そのユーモラスな姿は、人間社会と自然が交わる場所に生きる動物ならではの魅力です。 タヌキは、自然環境の変化にも敏感です。 森林の減少や都市化によって生息地が分断される中、食べ物を求めて人里近くに現れることも増えました。 これは生態系のバランスの一端を示す現象でもあり、人間とタヌキの共生について考えるきっかけとなります。 夜の里山で静かに動くタヌキの姿は、私たちに自然の奥深さを教えてくれます。 その柔軟で賢い生き方は、厳しい環境の中でも生き延びる知恵の結晶。 里山の風景に溶け込むタヌキは、小さくともたくましい、自然界の知恵者なのです。